【要介護認定】
申請からサービス利用までの流れ
ケアリエコラム>介護制度関連
.png)
年齢を重ね介護が必要な状態(以下、要介護状態)となり、介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。
しかし初めて認定を受ける方のなかには、「要介護認定とはいったい何」、「どのような順序で認定を受ける?」「必要書類は?」と疑問に思う方もおられるでしょう。
この記事では、要介護認定の受け方、判定、サービス利用までの流れ・プロセスを説明します。
要介護認定とは
要介護認定とは、要介護状態にある方の心身機能がどの程度なのか、市町村が調査を行い、その度合い(区分)を認定する仕組みを指します。
要介護認定を受けた高齢者は、自身が介護を必要とする度合いによって「自立」、「要支援1・2」、「要介護1~5」のいずれかに判定されます。
要介護認定の申請方法
要介護認定の申請をする場合、どこへ、どのような方法で行えば良いのでしょうか。ここでは、申請先、申請の方法、必要書類について解説します。
要介護認定の申請先
要介護認定の申請は、認定調査を受ける方が住む市町村役場で行います。申請を受け付けてくれる窓口の名称は、「介護保険課」などが一般的ですが、市町村によって異なるのが現状です。
申請に必要な書類
一般的に、申請には次の書類が必要とされます。ただし、市区町村によって必要とする書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。
代理申請の方法
要介護認定の申請は、原則として本人が行います。しかし、事情があって本人の申請が困難な場合(例:入院中、体調不良で窓口に来れない等)は、以下の人・機関が代理申請をすることができます。
申請からサービス利用までの流れ
申請した後、どのような流れで審査・判定が行われ、サービス利用までにどのくらい時間を要するのかを説明します。申請後の流れは次のとおりです。
以下、一つずつ見ていきましょう。
1. 訪問調査
訪問調査とは、市町村の担当者が申請者本人の自宅を訪問して行われる聞き取り調査です。訪問調査では本人の身体・精神に関する項目を調査するとともに、その他の特記事項(持病が日常生活に与える影響など)について記録します。所要時間は30分~1時間程度です。
2. 主治医の意見書を作成
要介護認定の申請を受けた市町村は、1の訪問調査と並行して、申請者の主治医に「意見書」の作成を依頼します。
主治医の意見書には、申請者の身体・精神に関する疾患、障害の有無、状態が記載されます。
3. 一次判定
市町村の担当者が、1の「訪問調査」で得られた内容・情報をコンピュータへ入力し、介護を必要とする度合いを数値化します。前述のとおり、申請者が自立した状態でなければ、要支援1・2または要介護1~5のいずれかに判定されますが、あくまでも仮判定という扱いで次に進みます。
4. 二次判定
2の「主治医の意見書」と、3の一次判定の結果を基に、市町村に設置される介護認定審査会が二次判定を行います。
介護認定審査会とは、医療・福祉・介護分野の有識者・有資格者等(医師、看護師、社会福祉士、介護支援専門員等)が5人1組の合議体で話し合い、申請者がどの程度介護を必要とする状態なのか、最終審査・判定を行う機関です。
5. 結果の通知
結果は、申請した日から30日以内に申請者の自宅へ郵送で通知されます。「自立」、「要支援1・2」、「要介護1~5」のいずれかに認定されますが、「自立」と認定された場合は、原則として介護保険サービスを利用することはできません。
6. サービス利用
要支援以上と認定され、介護保険サービスを利用を希望する場合、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、本人や家族の抱えるニーズ、課題、希望を聞き取ったうえでケアプランを作成します。このケアプランに基づいて、介護サービスを利用します。
まとめ
これまで要介護認定の受け方、流れ、サービス利用までのプロセスについて解説してきました。
近い将来、要介護状態となった場合に備えて、どのような方法で要介護認定が行われ、どのような区分に判定されるのか十分に理解しておきましょう。
-施設探し・介護のご相談は介護コネクトにお任せください-
\お電話からのご相談はこちら/
\WEBからのご相談はこちら/
この記事の関連記事
.png)
施設見学レポート② 「介護付き有料老人ホーム カルナシア菊水」様
皆様こんにちは、あなたのケアリエ和田でございます…
皆様こんにちは、あなたのケアリエ和田でございます…
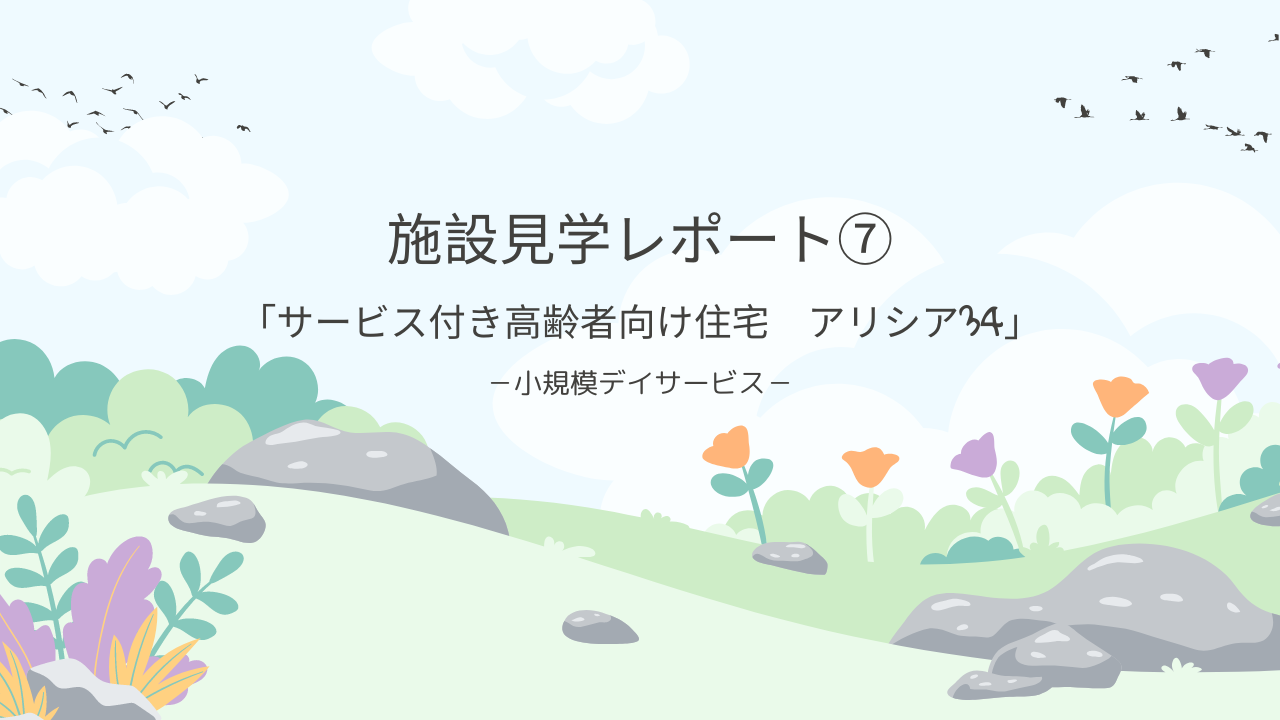
施設見学レポート③ 「サービス付き高齢者向け住宅 アリシア34」様
皆様、こんにちはあなたのケアリエ和田でございます。 …
皆様、こんにちはあなたのケアリエ和田でございます。 …
.png)
【札幌市の高齢者支援】介護保険サービス以外に札幌市が行っている12の支援
札幌市は、高齢者が安心して生活を送れるよう、介護保険サービス…
札幌市は、高齢者が安心して生活を送れるよう、介護保険サービス…
.png)
【要介護5とは?】自宅介護は可能?入居可能な介護施設、ケアプラン例を解説
要介護5は7区分に分かれている要介護認定区分のうち、最も重い…
要介護5は7区分に分かれている要介護認定区分のうち、最も重い…
.png)
【要介護4とは?】要介護5との違い、入居可能な介護施設、ケアプラン例を解説
要介護4は、7区分に分かれている要介護認定区分のうち、上から…
要介護4は、7区分に分かれている要介護認定区分のうち、上から…
.png)
【自動車運転免許証を返納するタイミング】4つの具体例と返納後も活用できる地域のサポートを解説
日本の高齢化が進む中で、多くの高齢者が運転を続けています。 …
日本の高齢化が進む中で、多くの高齢者が運転を続けています。 …
.png)
【札幌市の認知症支援】3つの支援と認知症高齢者が入居可能な施設を解説
札幌市は、認知症の高齢者やそのご家族などが安心して生活を送れ…
札幌市は、認知症の高齢者やそのご家族などが安心して生活を送れ…
.png)
【老後の一人暮らし】満足度や不安、一人暮らしを楽しむポイントを解説
近年、老後の一人暮らしの世帯数が増加傾向にあります。 これ…
近年、老後の一人暮らしの世帯数が増加傾向にあります。 これ…





